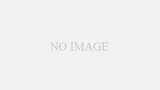子どもの将来のために欠かせない「教育費」。
しかし、進学のたびにかかる大きな出費に備えるのは、なかなか簡単なことではありません。
そこで重要なのが、制度の活用+日常的な貯金の習慣です。
この記事では、教育費を無理なく賢く準備するために、知っておきたい支援制度や金融商品、日常の貯金術まで幅広く解説します。
教育費ってどのくらいかかるの?
文部科学省の調査によると、子ども1人あたりにかかる教育費の目安は以下の通りです。
- 小学校(公立):約200万円(6年間)
- 中学校(公立):約150万円(3年間)
- 高校(公立):約150万円(3年間)
- 大学(国公立):約250〜300万円(4年間)
つまり、大学まで通わせるには最低でも700〜800万円はかかる計算になります。
これに私立や塾代が加わると、さらに上振れする可能性も。
利用できる支援制度を知っておこう
1. 児童手当
0歳から中学校卒業まで支給される国の制度。
所得制限はあるものの、毎月10,000〜15,000円を受け取れます。
このお金を手をつけずに積み立てるだけで、15年間で約200万円に。
2. 高等教育の修学支援新制度
一定の所得以下の世帯を対象に、授業料減免+給付型奨学金が受けられる制度です。
高校・大学進学時に該当する可能性があるなら、事前に調べて申請準備をしておきましょう。
3. 地方自治体の助成制度
自治体によっては、高校入学準備金や通学支援金などの制度があります。
お住まいの自治体のホームページで「教育費 補助」などと検索して確認しましょう。
制度だけでは足りない?金融商品も検討しよう
1. 学資保険
教育費専用の積立保険で、一定期間払い込むと満期時に保険金が受け取れます。
- 契約者に万が一があった場合、保険料の支払いが免除される
- 保障内容によって返戻率が異なるため、比較検討が必要
2. ジュニアNISA(〜2023年終了)
廃止されましたが、既に口座を持っている人は2024年以降も非課税で保有可能です。
3. つみたてNISAを活用する
長期・分散・積立投資で、10年後〜20年後の教育費を備えるにはうってつけ。
リスクはあるものの、預金では追いつかないインフレ対策にもなります。
日常の貯金術で着実に備える
1. 先取り貯金を習慣化
毎月の給料日に、まず教育費専用口座に一定額を自動振替するのがおすすめ。
2. お祝い金やボーナスは貯金に回す
入学祝い、児童手当、年末調整の還付など、“臨時収入”は全額教育費口座へ。
3. 家計簿で管理+家族で共有
目標額を「見える化」し、家族で協力しながら貯めるとモチベーションもUP。
まとめ
教育費は決して「突然必要になるお金」ではありません。
だからこそ、制度・保険・投資・日常の貯金術を組み合わせて、計画的に備えることが大切です。
まずは「いくら必要か」「何年後に必要か」を明確にし、今できることからスタートしてみましょう。
子どもが安心して夢を追える未来のために、親としてできる備えを、今日からはじめてみませんか?