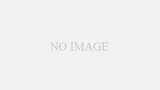突然の入院や手術、大きな病気の治療で、高額な医療費がかかることは誰にでも起こり得ることです。
「医療費が払えないかもしれない」と不安になる前に、ぜひ知っておきたい制度が「高額療養費制度」です。
この制度を正しく理解しておくことで、医療費の負担を大幅に軽減でき、精神的な不安もぐっと減らすことができます。
この記事では、「高額療養費制度」の基本から、実際にどれだけ得になるのか、申請の流れまでをわかりやすく解説します。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、1ヶ月あたりの医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
国民健康保険・社会保険など、すべての公的医療保険に加入している人が対象です。
制度のポイント
- 対象は「同じ医療機関・同じ月内」の自己負担額
- 支払額が「自己負担限度額」を超えた分をあとから返金
- 年齢・所得によって限度額が異なる
自己負担限度額の目安(70歳未満の場合)
厚生労働省によると、2024年現在の自己負担限度額は以下の通りです。
- 年収約370万~770万円:月の上限 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%
- 年収約1160万円超:月の上限 約252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%
- 低所得者:35,400円(または24,600円)など
つまり、どれだけ高額な治療を受けても、自己負担額には上限が設けられているのです。
実際にいくら戻ってくる?
たとえば、月に50万円の医療費がかかり、3割負担で自己負担額が15万円だった場合…
年収500万円程度の方なら、自己負担限度額は約9万円程度。
差額の6万円が、後日払い戻される仕組みです。
事前に「限度額適用認定証」を使うと便利
あとから払い戻されるのではなく、最初から上限額までの支払いに抑える方法もあります。
限度額適用認定証とは?
加入している健康保険に申請することで発行され、病院窓口で提示すれば、自己負担額を上限額までに制限してくれます。
入院や高額治療が事前にわかっている場合は、あらかじめ取得しておくと家計への負担を軽減できます。
高額療養費制度の申請方法
- 医療費の支払いを終える(後日、領収書を保存)
- 加入している健康保険組合に申請用紙を提出
- 必要書類(領収書、口座情報など)を添付
- 通常1〜3ヶ月後に指定口座へ返金
※申請期限は診療月の翌月初日から2年間。早めに手続きをしましょう。
世帯合算も可能です
同じ世帯内で、複数人が医療費を払った場合も「合算」して計算することができます(同一の健康保険加入者に限る)。
例えば、夫が5万円・妻が4万円・子どもが3万円支払った場合、合計12万円として計算可能です。
高額療養費制度の注意点
- 差額ベッド代や食事代は対象外(純粋な治療費のみ)
- 自由診療や美容目的の治療は非対象
- 月をまたぐと合算されないので注意
まとめ
高額療養費制度は、医療費が高額になったときに頼れる公的なサポート制度です。
「万が一」のときでも、この制度を知っているかどうかで、家計や精神的な安心感が大きく変わります。
自分や家族に医療費がかかりそうなときは、ぜひ早めに健康保険組合や市区町村の窓口に相談し、申請や認定証の準備をしておきましょう。
知っているだけで守れるお金がある――
それが「高額療養費制度」です。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
制度・控除・還元テクニックまとめ|知らないと損するお金の裏技集