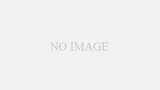産休・育休中は、出産や子育てに集中できる大切な時期。
しかし、収入の減少や出費の増加が気になる時期でもあります。
「収入が減るのにお金がかかる…」「どうやってやりくりしよう…」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、産休・育休中を安心して乗り越えるための貯金戦略とお金の使い方のコツを詳しくご紹介します。
1. 産休・育休中にかかる主な出費を把握しよう
まずは、どんな支出が増えるのかを整理しておきましょう。
- 出産費用(健康保険からの出産育児一時金あり)
- ベビーグッズの購入費(ベビーベッド、服、哺乳瓶など)
- おむつ・ミルク・消耗品
- 医療費・健診費用
- 外出が減る分のネット通販・デリバリー支出
月々の支出バランスも変わるので、一度家計を見直すチャンスでもあります。
2. 収入はどうなる?育休中に受け取れるお金
会社員や公務員であれば、「出産手当金」や「育児休業給付金」を受け取れるケースが多いです。
- 出産手当金:産前42日・産後56日間、給与の2/3が支給
- 育児休業給付金:育休開始から180日間は月給の約67%、それ以降は50%(上限あり)
これらの金額や時期を把握して、「いくら貯金が必要か」を逆算して計画しておくと安心です。
3. 産休前にやっておきたい“貯金準備”
収入が減る前に、できる準備をしっかり整えましょう。
実践ポイント:
- 固定費の見直し(スマホプラン、保険、サブスクなど)
- 臨時出費に備えた「生活防衛資金」を3〜6ヶ月分確保
- ベビー用品は必要最低限からスタート。後で買い足す
- 親・友人からのおさがりやレンタルも活用
「今は買わない」「あるもので代用する」意識を持つことで、出費を抑えられます。
4. 産休・育休中の“使い方のコツ”
収入が限られる時期だからこそ、お金の“使い方”にもメリハリが大切です。
コツ1:支出は「必要・欲しい・無駄」に分ける
- 「必要」=医療費・育児用品
- 「欲しい」=育児グッズや便利家電
- 「無駄」=衝動買い・ストレス発散の買い物
まずは「必要」から優先して管理。
「欲しいもの」は本当に必要か、買う前に一呼吸置いて考えましょう。
コツ2:育児支援制度をフル活用
- 児童手当(月1.5万円〜1万円)
- 自治体の出産応援ギフト・育児支援制度
- 医療費助成・予防接種の無料化など
意外と見落としがちな自治体サービスは、市役所や母子手帳配布時に確認を。
5. 将来を見据えた家計リセットのチャンスに
産休・育休中は生活スタイルが大きく変わる時期。
だからこそ、「これまでの支出を見直すいい機会」でもあります。
たとえば…
- 生活リズムに合わせて電気・ガスのプランを見直す
- 外食・交際費が減る分、支出構成も変化
- 家計簿アプリで“見える化”して把握力を強化
このタイミングでの家計の最適化は、育児後も続く「無理なく貯まる仕組み」づくりに繋がります。
まとめ
産休・育休中は、収入が減る一方で支出が増える時期。
だからこそ、「事前の貯金準備」と「使い方の工夫」が必要不可欠です。
とはいえ、無理に我慢ばかりする必要はありません。
知識とちょっとした工夫で、安心して大切な時間を過ごすことができるはずです。
家族の新しいスタートに向けて、今からしっかりと準備を始めましょう。
まとめたページもご用意しています。ぜひご覧ください。
ライフイベントに合わせたお金の工夫ガイド|人生の節目を賢く乗り切る知恵